※本記事はプロモーションを含みます。
「脂質=太る・体に悪い」と思っていませんか?
実は脂質には、**健康を守る“良い脂質”とリスクを高める“悪い脂質”**があり、その違いを理解することで、生活習慣病の予防や美容・ダイエットにも大きな効果が期待できます。
この記事では、脂質の種類ごとの摂取基準量と最新の科学的知見をもとに、健康的な脂質摂取のポイントをわかりやすく解説します。
脂質の分類と「良い・悪い」の科学的根拠
1. 飽和脂肪酸(制限すべき脂質)
-
摂取基準:総エネルギーの7%未満(厚生労働省「食事摂取基準2020年版」)
-
主な食品:牛・豚の脂身、鶏皮、バター、チーズ、パーム油など
-
健康への影響:
-
LDLコレステロール(悪玉)の増加
-
動脈硬化や心疾患リスクの上昇
-
脂質異常症を招くおそれ
-
※近年では、飽和脂肪酸の種類によっては必ずしも「悪」とは言い切れないという研究も。ただし、現時点では心血管リスク軽減のため摂取制限は継続推奨です。

2. トランス脂肪酸(最も避けるべき脂質)
-
摂取基準:総エネルギーの1%未満(WHO)
-
主な食品:マーガリン、ショートニング、スナック菓子、揚げ物など
-
健康への影響:
-
LDL増加+HDL(善玉)減少
-
心疾患・脳梗塞リスク増大
-
炎症性疾患や糖尿病のリスク上昇
-
👉 できる限りゼロに近づけるべき脂質です。

3. 不飽和脂肪酸(積極的に摂るべき脂質)
3-1. 一価不飽和脂肪酸(オメガ9系)
-
主な食品:オリーブオイル、アボカド、ナッツ、豚肉・鶏肉
-
メリット:
-
LDLコレステロールを低下
-
抗炎症・抗酸化作用
-
血糖値の安定
-

3-2. 多価不飽和脂肪酸(オメガ6系)
-
摂取基準:男性8〜10g/女性7〜8g(目安)
-
主な食品:大豆油、コーン油、ナッツ類
-
メリット:
-
細胞膜の構成成分
-
コレステロール調整
-
-
注意点:
-
摂りすぎると炎症を促進
-
オメガ3との比率がカギ(理想は4:1)
-

3-3. 多価不飽和脂肪酸(オメガ3系)
-
摂取基準:男性2.0〜2.2g/女性1.6g
-
主な食品:青魚(EPA・DHA)、えごま油、亜麻仁油、くるみ
-
メリット:
-
心疾患・脳血管疾患リスクの大幅な低下
-
抗炎症・血栓予防・うつ病予防
-
認知機能の維持に重要
-

実践的な脂質摂取のガイドライン
✅ 理想の脂質バランス
-
総脂質量:総エネルギーの20~30%
-
飽和脂肪酸:7%未満
-
トランス脂肪酸:1%未満(可能な限りゼロ)
-
オメガ6:オメガ3比率:理想は4:1
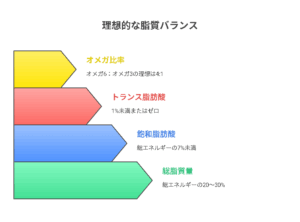
✅ 日常的に増やすべき食品
-
青魚(サバ・イワシなど)を週2〜3回
-
えごま油・亜麻仁油を小さじ1/日
-
くるみなどのナッツ類を適量
-
調理にオリーブオイルを活用
❌ 減らすべき食品
-
肉の脂身、鶏皮
-
揚げ物・ファストフード
-
加工食品・スナック菓子
-
マーガリン、ショートニングを含む製品
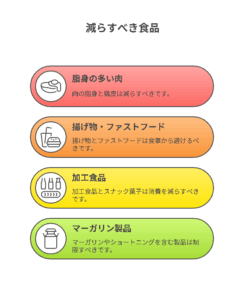
最新の研究から見えてきたこと
▶ 飽和脂肪酸は一括りに「悪」ではない?
-
中鎖脂肪酸(ココナッツオイル等)はエネルギー源として有用との研究も。
-
しかし、現行の摂取基準では心血管疾患予防のため制限が基本。
▶ オメガ3脂肪酸の圧倒的メリット
-
心疾患死亡リスク:約20〜30%減
-
脳血管疾患リスク:約15〜20%減
-
認知症リスク:約25%減
-
ただし酸化しやすいため、新鮮な魚やオイルの活用を優先
まとめ:脂質は“敵”ではない、賢く選ぼう!
脂質は健康に不可欠な栄養素です。「悪い脂質は減らし、良い脂質は積極的に摂る」ことで、生活習慣病の予防、アンチエイジング、脳と心の健康維持にもつながります。
脂質を「制限する」のではなく、「選ぶ」こと。
これが健康への第一歩です。

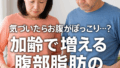
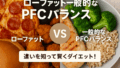
コメント